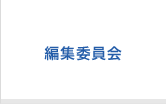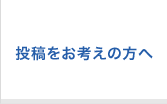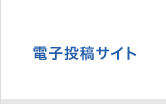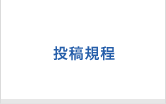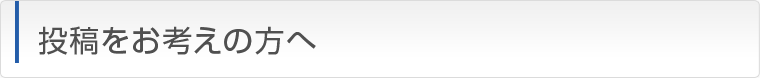- ホーム
- 投稿をお考えの方へ
編集後記より
三澤編集委員長の下,昨年より編集幹事を拝命いたしました.伝統ある「臨床神経学」の編集に携わることができるのは大変光栄であり,同時にその責任の重さを痛感しております.
近年,症例報告を受け付ける医学雑誌は商業誌を含め減少傾向にあります.とりわけ邦文による症例報告は,これから臨床や研究の道に進む若手医師にとって,最初の論文執筆の場となることが多いはずです.本誌は,質の高い原著論文を数多く掲載していることはもちろんですが,広く症例報告を受け付けている数少ない邦文臨床神経学系雑誌として,重要な役割を担っていると自負しております.本誌の症例報告は,邦文で本文5,000 字あるいは英文で2,000語と十分なボリュームを確保しており,図表を最大6 点まで使用できる点が大きな特徴です.これほど多くの図表を症例報告で使用できる雑誌は少なく,貴重な症例のディテールを共有する上で大きな強みとなります.また,内容に応じてより短い「短報」や「Picture in Neurology」を選択することも可能です.
ここで,図表の作成に関してひとつ提案があります.近年の若い先生方は,J-OSLER 等の影響もあり症例をまとめる能力が非常に長けていると感じます.一方で,投稿原稿の図表のなかには,「美しさ」に無頓着,あるいは「伝えたい意図」がはっきりしないものを時折見かけます.図表は論文の「顔」になり得ます.検査記録を単にスキャンしたものや,スライド発表の資料をそのまま転用したものは(意図的な場合を除き)避け,図表から自分が何を読者に伝えたいのかをよく吟味して,図の大きさやデザインを考えてみてください.「臨床神経学」には,お手本となる美しい図表を用いた論文が多数掲載されています.洗練された図表が完成すると,論文執筆へのモチベーションも自ずと高まります.ぜひ,「美しい図」とともに,皆様の貴重な経験を「臨床神経学」へご投稿いただけることを心よりお待ちしております.
(國分 則人)
投稿者へのアピールポイント
日本の神経内科学のリーディングジャーナルとして
- ★PubMed/MEDLINEにabstractだけでなく、全文が収載されています。
- ★日本の神経内科学のリーディングジャーナルとして、年間320万件以上(2025年集計)のアクセスがあります。
- ★2015年からオープンアクセスジャーナルになり、アクセス数の増加、被引用論文として有利な状況となっています。
- ★毎月、最新号のメール目次が会員へ配信されています。
- ★2015年5月J-STAGEにてから早期公開を開始しています。
- ★2022年5月から著作権の面でもオープンアクセスとなり、掲載された図表は学術目的であれば、申請せずに他紙や学会発表で転載利用できるようになりました。
若手医師の登竜門として
- ★卒後間もない先生方に発表の場を提供しています。
- ★投稿論文は温かく育てましょうという理念の下、査読は極めて教育的、建設的に行われています。
- ★査読が迅速です(昨年度の初投稿原稿の平均査読日数は10日間)
症例報告が多く掲載されています
- ★日々の診療に直接役立つ、日本語での症例報告を多く掲載しています。
- ★図と表を合わせて最大6個も掲載できるので、多くの情報を共有できます。完全電子化により、カラー代も無料です。
- ★Letters to the Editorを通して、発表された症例を討議することができます。
その他
- ★英文投稿も受け付けています。