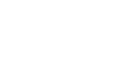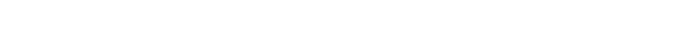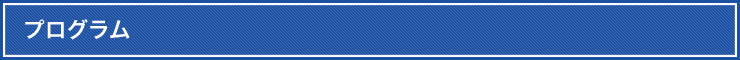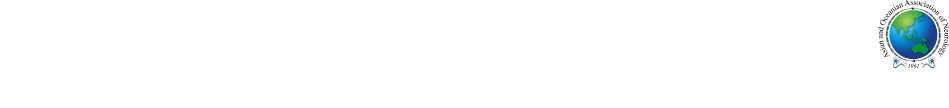- ホーム
- プログラム
- 教育コース「ねらい」一覧
教育コース「ねらい」一覧
- ・教育コース
-
5月29日(水)9:50~11:50 / 13:20~15:20
5月30日(木)9:15~11:15 / 15:30~17:30
5月31日(金)9:45~11:45 / 15:00~17:00
6月 1日(土)9:45~11:45 / 15:00~17:00
教育コース
5月29日(水)9:50~11:50
EC-01
テーマ:臨床遺伝の基礎―家系図を書け、遺伝学的検査の結果を解釈できるようになる!―
ねらい:脳神経内科領域には、遺伝性の神経筋疾患が多く含まれます。遺伝学的検査の保険適用も拡大し、脳神経内科医が日常診療の中で遺伝学的検査を実施する機会が増えています。生殖細胞系列の遺伝情報には、不変性、予測性、共有性という特性があり、その特性を理解した上で、家系図を作成し、適切に遺伝学的検査・診断を実施していく必要があります。主治医自身が遺伝学的検査の結果を解釈して、患者に説明し、今後の診療計画を考えていくことが求められるようになりました。本コースは、主治医が自分で家系図を書き、遺伝学的検査結果を解釈して患者・家族に説明できる力を身につけることを目的として行います。本コースで学ぶ国際標準の家系図作成法、遺伝子解析方法の理解、遺伝子バリアントの表記法ならびにバリアントの評価方法は、明日からの診療のみならず、論文の理解や作成にも役立ちます!
[対象] 初級~上級
EC-02
テーマ:脳表ヘモジデリン沈着症の最新知見
ねらい:特発性脳表ヘモジデリン沈着症は、主に硬膜瘻孔と剥離による硬膜内の血管からの間欠的微量出血により、脳や脊髄表面にヘモジデリンの沈着がみられ、感音性難聴,小脳性運動失調,脊髄症,認知機能障害などの症状をきたす。最近の研究で、多くの特発性脳表ヘモジデリン沈着症に認められる硬膜瘻孔と硬膜の層状剥離が硬膜内静脈からの出血の原因となっていることや、上肢の近位筋萎縮を伴う症例における硬膜瘻孔閉鎖術の有効性、鉄キレート剤の有効性などが報告されている。本コースでは、脳表ヘモジデリン沈着症の疫学、病態生理、画像所見、治療法などについて、最新の知見を多くの先生に知っていただくことで、関連各科の協力が重要であることを理解していただけることを期待している。
[対象] 中級:神経内科専攻医(後期研修医)レベル
EC-03
テーマ:質問歓迎!エクスパートに聞こう、てんかん診療の極意
ねらい:てんかんは患者数が約100万人の脳神経疾患の高頻度疾患です。超高齢社会となり、脳神経内科医が診断と治療を担う役割が増してきています。的確な診断と治療により発作が抑制でき、「治る脳神経内科」の病気として、社会からも期待されています。背景疾患や発作症状は多岐にわたるため、患者さんを日々の外来で診ていると、診断や治療の悩みがでてくると思います。
「これって失神?てんかん発作?」、「病歴で何を聞けば、的確な診断に繋がる?」、「一剤目で発作が止まらない、どうしよう?」「薬剤抵抗性、難治だが、診断が合っているのか、やはり手術やデバイス治療の適応なのか?」といった疑問に、てんかん診療のエキスパートが実際の症例提示を通じて答えてくれます。司会・講師・参加者でinteractiveとなるコースを企画しました。これからてんかん患者さんを診る先生から、診療経験のある先生まで、奮ってご参加ください。
[対象] 初級~上級(正会員向け)
5月29日(水)13:20~15:20
EC-04
テーマ:脳神経内科と他科の関わり-脳神経内科医に必要な他科の知識,他科医に必要な脳神経内科の知識―
ねらい:以前にある大学の6年生の特別講義で「脳神経内科を制するものは国試を制す」と題する講義を行ったことがある.その理由は,純粋に脳神経内科の問題は全体の数%に過ぎないが,脳神経内科の知識があれば解ける問題を含めると15〜17%を占める.すなわち脳神経内科は,診療科の中で最も様々な科との関わりが強い診療科といえる.内科の他科以外にも脳神経外科や精神科はもちろん,整形外科,眼科,耳鼻咽喉科,泌尿器科とも密接な関係があり,それらの知識が必要とされる.また,他科疾患が神経症状を引き起こしたり,反対に神経疾患の経過中や治療において他科的合併症に遭遇する機会も多い.一方,他科との境界領域の疾患,病態や他科と共通する疾患も少なくない.本コースでは,まず他の内科領域との関わりや境界領域疾患について,ついで眼科,耳鼻咽喉科,泌尿器科,整形外科との関わりについて解説いただく.
[対象] 初級:医学生あるいは初期研修医
EC-05
テーマ:アクセプトされる論文の書き方
ねらい:第63回日本神経学会学術大会における教育コースで実施された「アクセプトされる論文の書き方のコツ」は、演者の一人、故木村 淳京都大学名誉教授の追悼教育コースとなり、京都大学脳神経内科のご協力とご好意によりご講演のビデオを上映することができ、初学者から専門医まで多くの幅広い年齢層の受講者に恵まれ、高い評価を得ることができました。第65回では、演者に日本神経学会の重鎮金沢医科大学名誉教授廣瀬源二郎先生をお迎えし、同趣旨で、教育コースを企画しました。初学者にとって論文執筆はなかなかハードルが高く、どのようにアプローチしていいか具体的な方策に迷うことが多いのが現実です。そこで、5人の論文経験の豊かな先輩から英文原著、和文原著、症例報告そして総説の書き方、研究成果の論文へのまとめ方の要点、他施設共同研究の成果の論文へのまとめ方のコツ、さらに投稿後に査読者の厳しい指摘に対する理路整然とした反論rebuttalの方法・記述の仕方についてもご指導いただきます
[対象] 上級:神経内科専門医 レベル
EC-06
テーマ:120分でゼンブ分かる!最新の脳卒中診療
ねらい:近年,脳卒中における診断と治療の躍進がめざましく,特に脳梗塞においては灌流画像とカテーテルを使用した再灌流療法が世界的に標準治療として定着した.しかし,脳卒中専門医以外はいまだにtPAや脳内カテーテルの適応のアップデートについていけないことを多々見聞する.初学者から初期研修医に至っては,必ず救急の現場で遭遇する脳卒中という疾患を,包括的にとらえ,かつ最新の標準治療を学べる120分にしたいと考えます.
[対象] 中級:神経内科専攻医(後期研修医)レベル (正会員向け)
5月30日(木)9:15~11:15
EC-07
テーマ:脳神経内科医が知っておくべき臨床薬理学の視点
ねらい:「臨床薬理学」とは「薬物の人体における作用と動態を研究し、合理的薬物治療学を確立するための科学」と定義され、薬物治療を行う脳神経内科医にとってもその素養が求められる学問領域である。しかしながら日本では、臨床薬理学講座が設置されていない大学も多く、卒後教育も含め脳神経内科医が臨床薬理学に触れる機会は少ない。そこで本コースでは、脳神経内科医が薬物治療を実践する上で必要な臨床薬理学のエッセンスについて、各領域のトップランナーの先生方に講演していただく。また将来の薬物治療へと繋がる医薬品の開発・臨床評価も臨床薬理学の重要な領域であり、臨床研究に関する最新の動向についても解説する。脳神経内科領域において合理的薬物治療を確立するためにも、本コースを入り口として活用していただきたい。
[対象] 初級~上級 (正会員向け)
EC-08
テーマ:今さら聞けない! 脳神経内科医のための睡眠医学ことはじめ
ねらい:海外の脳神経内科関連学会では,「睡眠」は脳神経内科医が学ぶべき主要なカテゴリーのひとつとして確立しています.一方日本の脳神経内科領域では,基礎研究での進歩は著しいものの,実地診療や教育を行える専門医・施設は限られています.我々は睡眠を専門とする神経内科医として,本教育コースをとおして継続的に脳神経内科医に睡眠診療の学びの場を提供していきたいと考えています.過去の教育コースでは「PSG」や「眠気の診かた」などさまざまなテーマを扱いましたが,参加者からのフィードバックからは,実際にはさらにプライマリーな知識を求められていることがわかりました.今回は臨床に最低限必要な睡眠生理や睡眠検査,スリープヘルスの知識から,脳神経内科医が実践する睡眠時無呼吸治療まで,基本中の基本を噛み砕いて,しかし大事なことは丁寧にお伝えしたいと思います.
[対象] 初級~上級
EC-09
テーマ:Interactive Neurological Clinico-Pathological Conference (CPC)
ねらい:神経病理学を理解することは難しいことは間違いありません。さらに、病理解剖数の減少から、診療に関わってきた患者さんの死後の病理所見に触れる機会は極めてすくなくなってきました。一方、神経病理の講演やテキストだけで、神経病理を理解することは難しいものです。臨床病理カンファレンス(CPC)も、しばしば1方向性になりがちです。このセッションでは、前半で臨床画像神経病理の基本的な内容のオーバービューを示します。基本的な疾患を中心に2名の先生による座学になります。臨床画像病理の関係を解説して、モダン神経病理学を解説します。後半は、前半の講義を生かして、双方向性CPCを2例行います。簡潔な臨床経過と神経病理解説、さらにCPC中に参加者はオンラインでクイズに回答をしていただきます。呈示には、バーチャルスライドなども駆使し、ダイナミックな呈示をしますので、顕微鏡をみているような感覚が得られるとおもいます。2時間という限られた時間で、神経病理の面白さに触れていただければさいわいです。
[対象] 中級:神経内科専攻医(後期研修医)レベル
5月30日(木)15:30~17:30
EC-10
テーマ:筋電図塾 in 東京
ねらい:筋電図塾は神経伝導検査や筋電図をもちいた臨床診断の基本をレクチャーや症例を通じて塾のように学ぶことを目的としてます。関西地区で60回以上続いている筋電図塾の学術大会バージョンで、これまでにも2回行いましたがいづれも好評でした。筋電図への苦手意識がある人も多いと思いますが、基本的な原理を理解していけば筋電図の解釈はそれほど難しくはなく、神経筋疾患の病態をリアルタイムで知ることができる素晴らしいツールです。その面白さや楽しさを伝えることができればと考えながらこれまでもやってきました。塾長(幸原)のミニレクチャー、若手医師からの症例プレゼンテーション(幸原、関口らとの対話形式)、教頭(関口)の筋電図、病理を含めた症例当てクイズ(neurogenic? or myogenic)で毎回行っています。初学者の立場に立った、「ためになった、おもしろかった」といってもらえる塾になることを目指して企画しています。
[対象] 初級:医学生あるいは初期研修医
EC-11 ★要事前予約
テーマ:君にも出来る!脳血栓回収療法ハンズオン
ねらい:脳主幹動脈の急性閉塞による脳梗塞に対して、機械的血栓回収療法は標準的治療となっている。発症から再開通までの時間を出来るだけ短縮することで後遺症が軽減されるため、脳神経内科医も血栓回収療法を含む脳血管内治療に関わる機会は多い。本ハンズオンでは、血管モデルを用いて実際にカテーテルや血栓回収デバイスに触れて、脳血管内治療についての理解を深めることを目的とする。脳血管内治療を自ら行ってみたいと考える医学生、初期研修医、本会会員が、脳神経内科医でも治療が行えることを知っていただきたい。
[対象] 初級~上級(正会員、非会員(医師・研究者)、初期研修医(会員・非会員)、医学生のみ事前予約可能)
[機材協力]日本ストライカー株式会社/日本メドトロニック株式会社
EC-12
テーマ:神経心理学的臨床推論:神経心理を診断・治療に役立てる
ねらい:神経心理検査をいろいろとやってみたものの、結果の解釈の仕方がわからない、得られた所見をどのように診断や治療につなげるのかわからない、と感じている臨床家は多いと思います。
本コースでは、神経心理学的診察や検査が病態評価が臨床現場での意思決定に決定に役立った症例を提示し、臨床推論の過程について参加者のみなさんと議論をいたします。日常臨床における神経心理学的評価の意義を知り、日常診療にすぐに応用できるようなアプローチを学んでもらうことを目指します。
[対象] 初級~上級
5月31日(金)9:45~11:45
EC-13
テーマ:これくらいは知っておこう、脳卒中リハビリテーションのミニマム知識
ねらい:脳神経内科医にとって、脳卒中は最も高頻度に遭遇する疾患のひとつである。脳卒中診療に対峙する医師ならびにメディカルスタッフには、脳卒中に対する急性期治療のみならず長期的なリハビリテーション(以下、リハ)の意義と内容を理解しておくことが望まれる。本コースでは、5人の演者がまずは脳卒中リハについて「最低限知っておくべき知識」を講義し、そのうえで理解を深めるために参加者からの質問を積極的に受け付ける。今回は特に、2023年に発表された脳卒中急性期リハの指針、長下肢および短下肢装具を用いた片麻痺に対する歩行訓練の実際、高次脳機能障害の評価とその対処方法、嚥下障害に対する評価と訓練の実際、新しいリハ治療である経頭蓋磁気刺激治療の最新知見にポイントを絞って講義を進める。実臨床において「若手医師やメディカルスタッフが、すぐに使える脳卒中リハの知識」を少しでも多く教示したい。
[対象] 初級:医学生あるいは初期研修医、メディカルスタッフ向け
EC-14
テーマ:臨床診断基準を満たした例の神経病理像の多様性
ねらい:臨床診断基準は生前診断の精度を最大化できると考えられてはいるが、多数例を病理で確認した研究はかならずしも多くない。一方で、臨床診断基準を満たしながら、病理像が異なる例や、臨床的には予見し難かった複合病理の存在に遭遇することもある。逆に臨床診断基準を満たさないながら、その病理診断が確定する例にもしばしば遭遇する。一旦臨床診断基準を満たしてしまうと、それ以外の可能性を検討せずに満足する一種の思考停止に陥る場合があり、病理学的検証を欠けば、あたかも最終診断として確定できたかのような錯覚におちいりかねない。臨床像だけから予見困難なこうした例外の臨床と病理を比較し、どうすれば生前診断の正診率を向上させることが可能かを検討する。基準に基づく操作的診断の限界をわきまえるだけでなく、病理像に臨床像からさらに肉迫するために、臨床診断基準以外にどのような点に留意すれば良いか議論したい。
[対象] 初級~上級 (正会員向け)
EC-15
テーマ:もう怯まない!小児期発症神経系疾患の成人移行を上手く引き受ける要諦
ねらい:診療水準の向上や社会基盤の発達に伴い,小児期発症疾患の予後が改善し,成人移行支援のニーズが高まっています。日本神経学会では2020 年に「小児-成人移行医療対策特別委員会」を設置し,日本小児神経学会と連携して,診療科連携推進や啓発,診療報酬での評価に向けた活動を行っています。しかし,理念や提言が先行する一方,診療現場では必ずしも円滑な成人移行が行われているとは言えません。克服すべき多様な要因の一つは「脳神経内科医にとって小児神経疾患の臨床像に馴染みが乏しく敬遠しがち」なことではないでしょうか。この企画では,成人移行が多い病態について,患者の生涯を見据えた全人的診療に長けた演者に引き受けの要諦をご講演いただき,成人移行に欠かせない社会支援制度を紹介します。ぜひ成人移行患者引き受けへの不安を払拭してください。(この教育コースは日本神経学会小児-成人移行医療対策特別委員会により企画しました。)
[対象] 初級~上級
5月31日(金)15:00~17:00
EC-16
テーマ:脳神経内科領域における臨床遺伝学x母性内科学〜挙児希望のある神経疾患患者にどのように対応するか
ねらい:今、NEUROLOGYには静かな革命が訪れている。革新的な病態研究と創薬は、多くの脳神経疾患を持つ患者に福音をもたらしている。一方、既存の経験では刃が立たない、新たな臨床的ジレンマへの対応を迫られる場面も多い。本シンポジウムでは、挙児希望を持つ脳神経内科疾患患者に焦点を当て、「臨床遺伝学」と「母性内科学」がタッグを組み、臨床的ジレンマへの対応を学ぶことを目的にした。本シンポジウムに参加する全員の声を集約しながら、未来にあるべきNEUROLOGYの姿を考えていきたい。
[対象] 中級:神経内科専攻医(後期研修医)レベル
EC-17
テーマ:基礎研究は楽しいよ!脳神経内科医のベンチワーク入門
ねらい:近年、神経疾患に関連する基礎研究の内容は非常に高度になっていますが、同時に日本の研究力の低下が問題視されています。このような状況から、高いレベルの研究を維持するためには研究マインドを持つ脳神経内科医の育成が求められています。しかしながら、専門医取得までの課程が複雑化し、多忙な生活によるワークライフバランスの圧力もあり、wet研究を志す脳神経内科医の数が減少していると実感されています。例えば、学部学生時代は研究室に関わっていても、研修医プログラムに入ると疲弊し、研究室を離れるケースも見受けられます。こうした問題を改善する一助として、本コースでは若手脳神経内科医を対象にし、研究に興味を持つ医師たちとwet研究に没頭してきた若手・中堅・ベテラン脳神経内科医とのパネルディスカッションを通じて、臨床と研究の両立の意義や楽しさを共有する場を提供したいと考えています。
[対象] 中級:神経内科専攻医(後期研修医)レベル
EC-18
テーマ:critical careの脳波のABC:特徴,判読のケーススタディー
ねらい:機器の進歩に伴い、難治てんかんのビデオ脳波モニターだけでなく、critical careの急性脳病態での脳波持続モニターが広く施行可能となり、特に後者では従前の急性症候性発作・重積にも新たな知見が明らかとなってきた。
急性意識障害・急性症候性発作の脳波では、神経細胞とアストロサイトの障害の程度の違い、脳虚血・代謝障害の並存など、慢性難治てんかんと比較した病態の違いが脳波所見をより複雑にしている。本コースでは、1)慢性てんかんとcritical careの脳波の特徴と判読の違いを明らかにして、2)一般臨床での脳波判読の結果を病因病態に応じて、適切に診断治療に反映させることができることを目的とし、3)主にケーススタディー形式で両者の判読の実際を症例検討方式で提示して理解を深める。
[対象] 中級:神経内科専攻医(後期研修医)レベル
6月1日(土)9:45~11:45
EC-19
テーマ:ディベートで深める頭痛の病態生理
ねらい:教科書の中に頭痛に関する記載も増え,頭痛を特集した参考書や専門書も増えてきましたが,初学者にとっては,わかりにくいことが記載されています.誰でも一度は経験する頭痛,日常診療ではとても多い頭痛ですが,臨床現場ではとっつきにくく,遠慮したいと感じている先生が少なくないのも事実です.
本教育コースでは,一次性頭痛の代表である片頭痛が抱えている2つのポイント,すなわち,(1)「片頭痛の病態は三叉神経血管説に矛盾しない」,(2)「片頭痛と緊張型頭痛は異なる疾患であり,同一線上の疾患ではない」について,ディベート形式で紹介し質疑することによって,理解しにくかった点や問題点,今後の課題をあぶりだしていきます.是非,質疑応答に積極的にご参加いただき,皆さんの頭痛の種を減らしてください.なお,ディベート形式とは,自分の意見に関係なく肯定・否定担当に分かれ,第三者に対して理論的に説得を行い,議論する手法です.
[対象] 初級:医学生あるいは初期研修医
EC-20
テーマ:症例を極める
ねらい:「症例を極める」は、簡単には診断がつかない症例を長年あきらめずにつきつめた結果、診断や治療にたどり着いた症例、病態の解明や新規疾患群の提唱に結びついた症例などを、教育にパッションがある先生方のプレゼンテーションを通して紹介し、専攻医や若手神経内科医に一つ一つの症例に向きあう大切さを伝えるセッションとしている。今回は髄膜炎、脳出血、筋力低下といった、一見よく遭遇する神経症状の中にある非典型な部分を手がかりとして、あらゆる角度から症例をつきつめ、類似症例を集め、基礎研究ともコラボレーションすることで、新知見に至った症例を集めた。突き詰めた結果、新たな疑問が生じ、そこに新たな研究意欲が生まれるところも紹介する。補体、自己炎症、神経筋接合部、病理など関連領域の知識を深めることができ、専門医の先生方にとっても十分興味深い構成とし、コメンテーターをおいて質疑応答のセッションを充実を計っている。
[対象] 中級:神経内科専攻医(後期研修医)レベル
EC-21
テーマ:脳神経内科疾患の摂食嚥下・栄養障害の病態と対策(疾患別特徴を学ぶ)
ねらい:脳神経内科疾患の多くに合併する、摂食嚥下障害・栄養障害は、療養上のQOLを損なうのみならず、誤嚥性肺炎・窒息など生命予後に直結する。摂食嚥下・栄養障害の病態や対策は、脳神経内科医として系統的に学ぶ機会は多くなく、日常診療で難渋することもある。日本神経摂食嚥下・栄養学会(JSDNNM)は2005年に研究会として発足してその後学会に改称し、19回の学術大会を経て臨床研究の実績を積み重ね、啓蒙活動も行ってきた。脳神経内科疾患の摂食嚥下・栄養障害について、脳神経内科のみならず関連の専門領域の医師や医療職とも連携している。本教育コースでは、JSDNNMの役員が講師となり、主な脳神経内科疾患における、疾患に特徴的な摂食嚥下・栄養の病態の知識と、臨床に還元できる医療的ケア・リハビリテーションのエビデンスを共有する。また、関連職種との連携の在り方についても、ともに考えることをめざす。
[対象] 初級~上級
6月1日(土)15:00~17:00
EC-22
テーマ:学生・初期研修医のための「症候・病態」から学ぶ実践的臨床神経学
ねらい:私たちは第62,63回学術大会教育コースにおいて,医学教育モデル・コア・カリキュラムや医師臨床研修指導ガイドラインの到達目標から4つの症候・病態を選び,症例ベースの「症候・病態」を双方向的プログラムを開催し、好評を得た.第65回大会でも、従来のように神経学に関連する項目,嚥下困難、排尿障害、発熱の3項目を題材に、神経専門医を目指す学生.初期研修医を対象に,医療面接,神経診察,臨床推論の基本をインターアクティブに身につけるセッションを実施したい.64回大会では,独自に実施した参加者アンケートで,神経診察の手技指導を希望する意見があった。そこで、今回は,より双方向性を高めるため,提示症例数を3に減らし,神経診察をハンズオンかつインターアクティブに教授する時間を手厚く配分する構成とした.最大のねらいは,この営みを通じて,初学者に臨床神経学への興味を深めてもらうことがであるが,これまでと同様に現場で指導に苦労している中堅以上の先生方と若手指導の方法について共有しあうことを「hidden curriculum」としたい.
[対象] 初級:医学生あるいは初期研修医
EC-23
テーマ:神経疾患の病状説明~どのようにわかりやすく、説得力を持って話すか~
ねらい:神経疾患の病状説明は日々行われている。しかし医学講義で「病状説明」を体系的に学ぶことはないし、標準化されたマニュアルがあるわけでもない。経験を重ねる中で、指導医や上級医の説明を参考にして組み立てているのが現状であろう。神経疾患は非常に幅広いため、対象疾患によって説明内容が著しく異なる。また他領域と比べると、一般の人にはわかりにくい部分が少なくないため、説明する言葉もより平易なものが求められる。本コースでは疾患として脳卒中、頭痛、認知症、重症筋無力症、遺伝性神経疾患(特に家族性アミロイドポリニューロパチー)、筋萎縮性側索硬化症を取り上げ、各疾患のエキスパートから病状説明の実際を解説していただく。各エキスパートの病状説明と自分のそれを比較していただき良い所、悪い所を討論していただきたい。本コースを通して参加者全員の病状説明の上達を目指したい。本企画は臨床医部会設置準備員会からの提案である。
[対象] 中級:神経内科専攻医(後期研修医)レベル
EC-24
テーマ:パーキンソン病のデバイス療法 update 対象は?方法は?
ねらい:パーキンソン病では、ドパミン補充療法後に、運動および非運動合併症をきたし、QOLの低下をきたすだけでなく、精神的、物理的、経済的負担となるほか、生命予後にも影響しかねない。その場合、現在、デバイス療法が選択肢として挙がるが、その療法を選択するか、またどのタイミングで、適応は?など、パーキンソン病診療に詳しくない場合、迷うことも少なくない。また良くわからない故に、患者さんがその恩恵に預かれないことも想定される。そこで、パーキンソン病を診療するすべての脳神経内科医に、パーキンソン病のデバイス療法の知識を深めてもらい、必要時、適切にデバイス療法を患者さんに提示できるようになればと思い、本コースを発案した。
[対象] 初級~上級